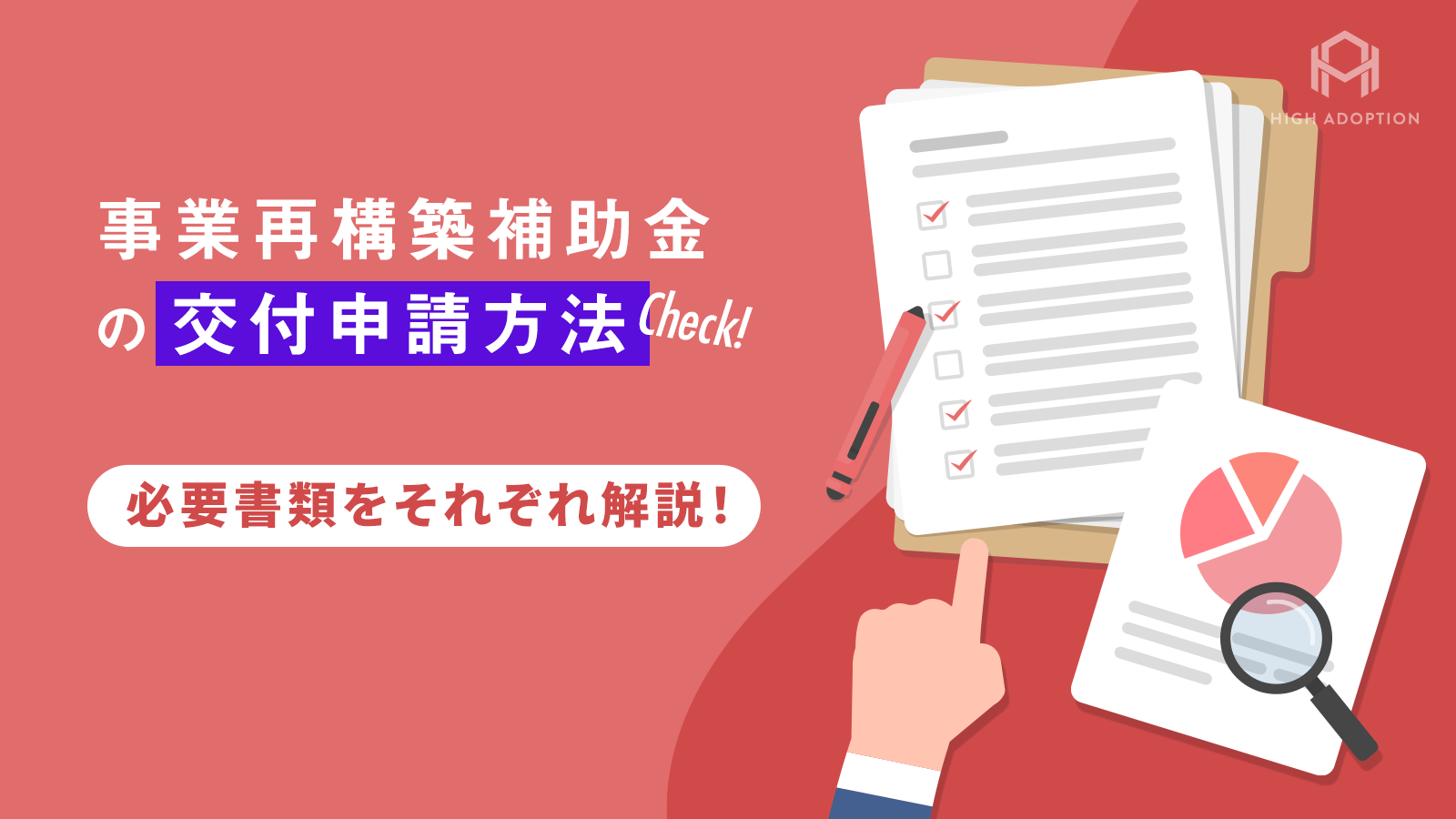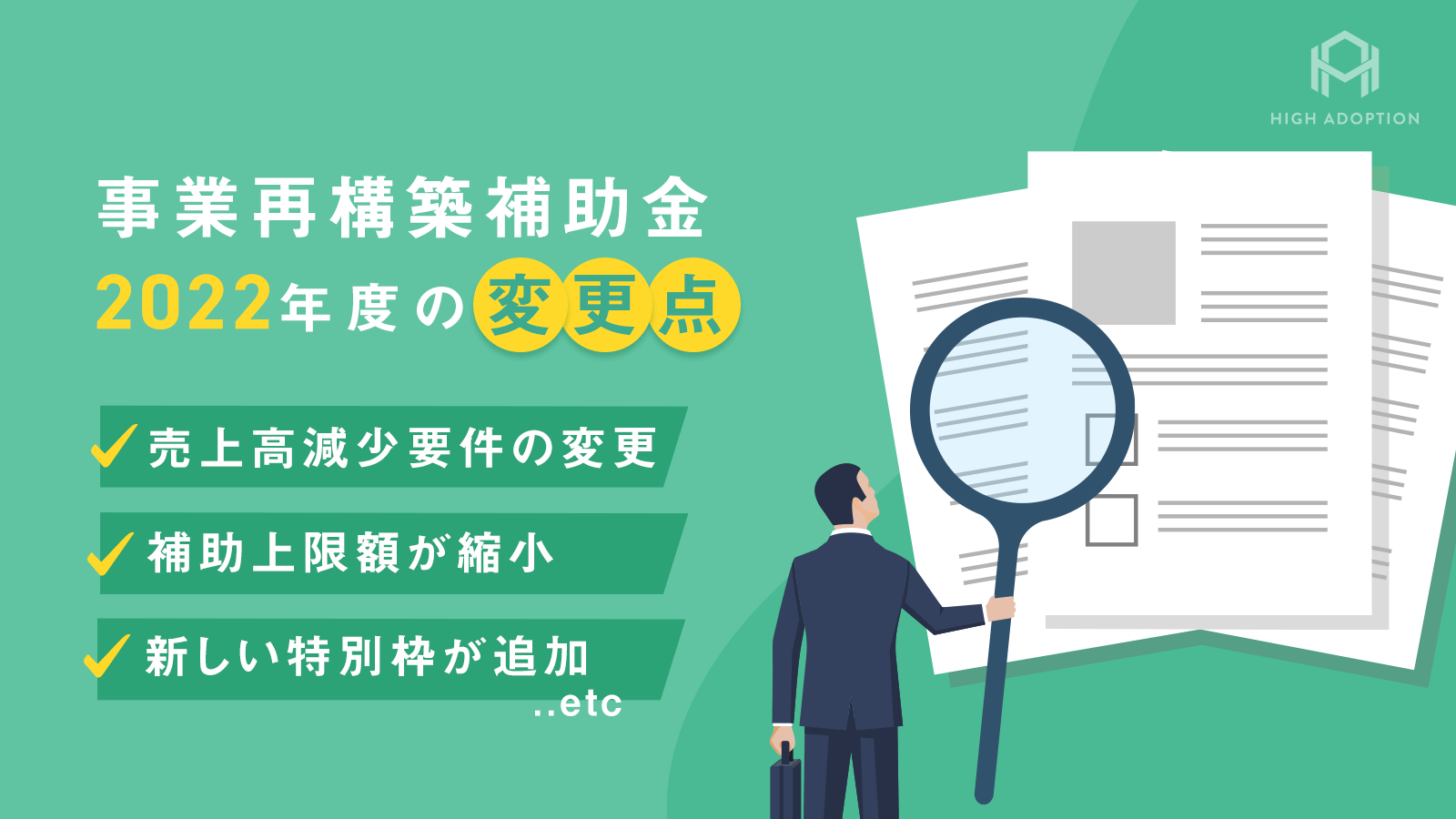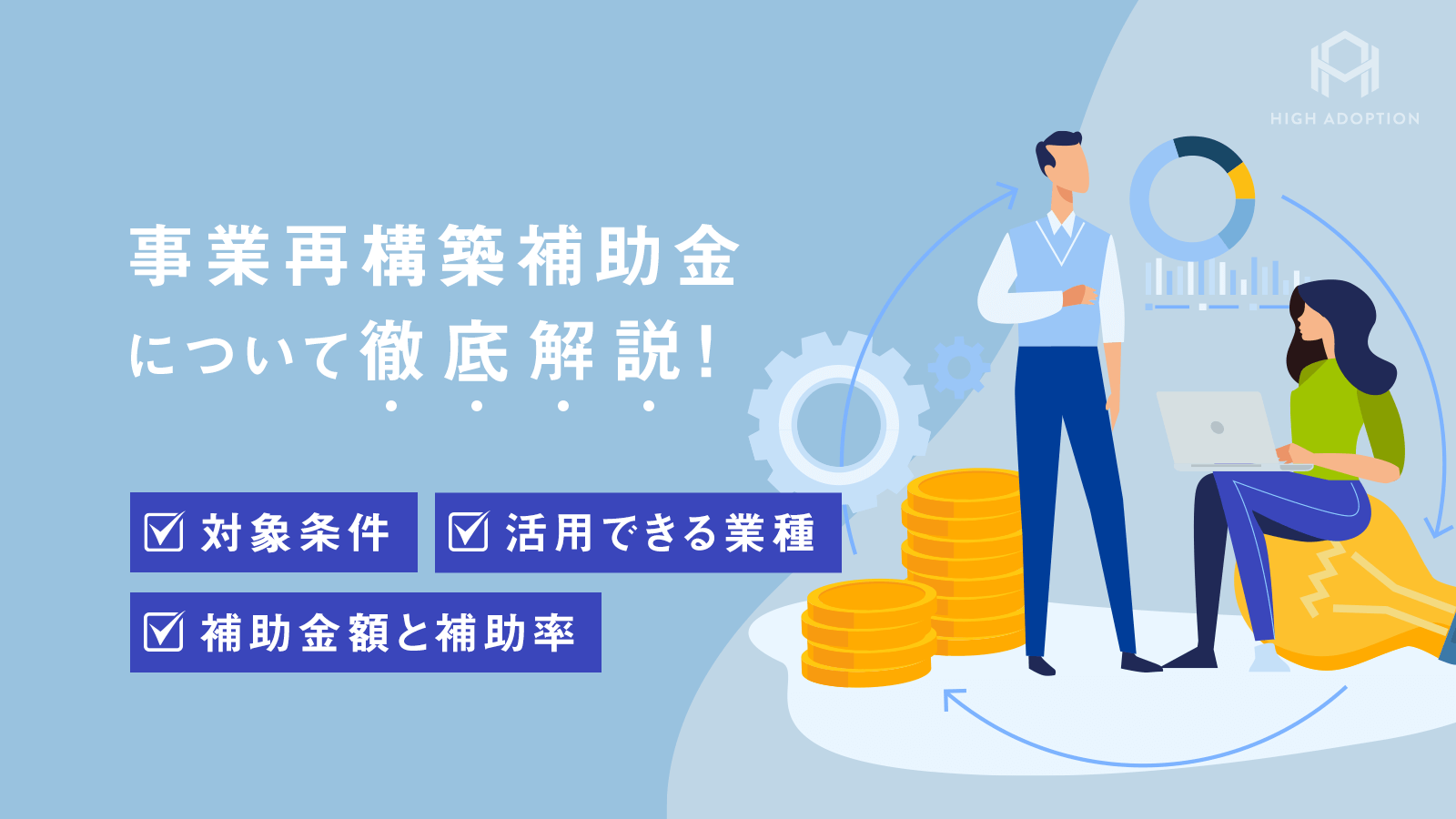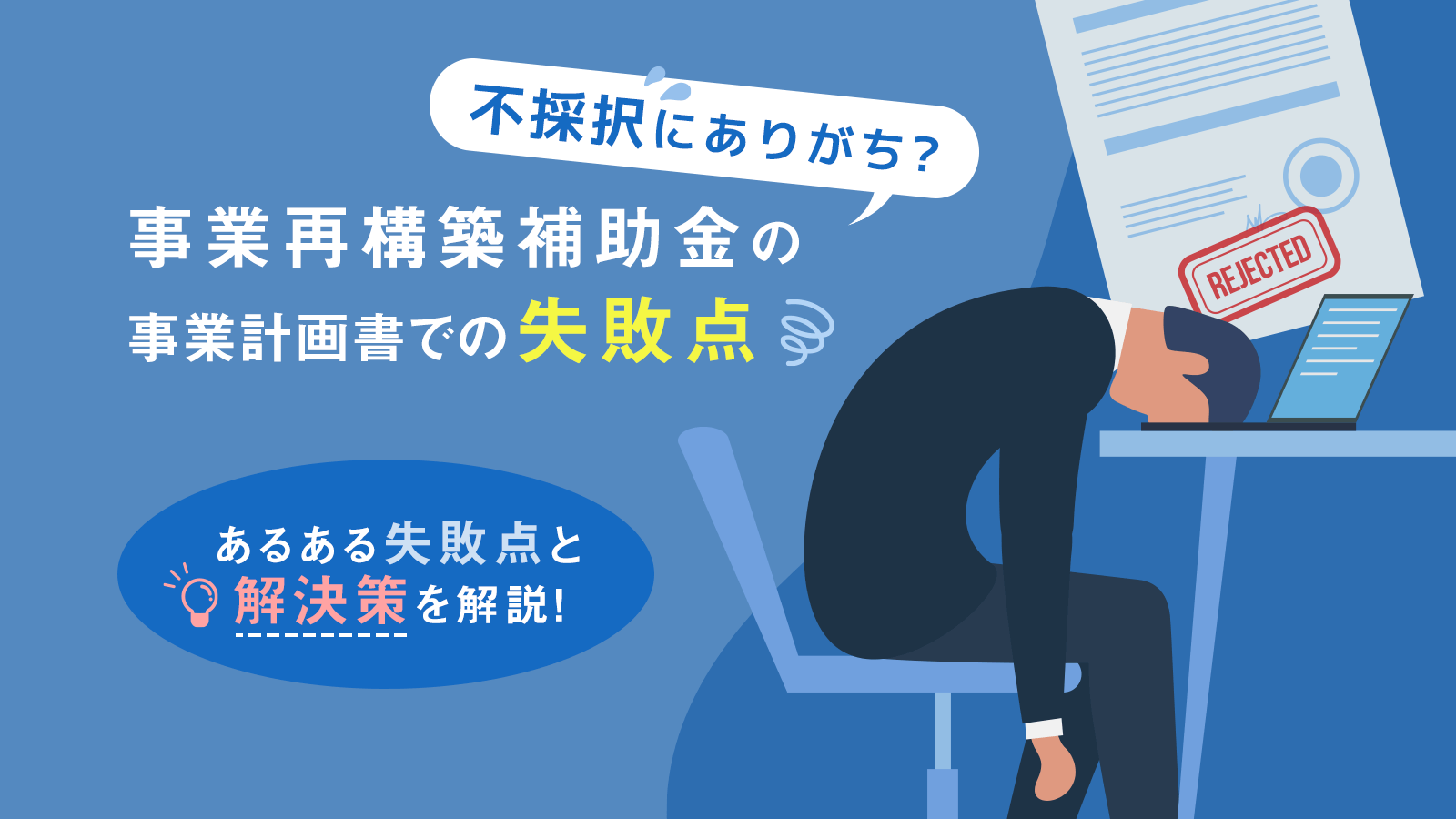
事業再構築補助金の採択率は30~50%程度であり、あまり高い数字とは言えません。そこで今回は、不採択にありがちな失敗点などを紹介した上で、採択されるための改善方法について詳しく紹介します。
事業再構築補助金が不採択になる要因
事業再構築補助金が不採択になる理由は企業によってさまざまですが、その理由は大まかに3つの要因にまとめられます。ではまずその要因について詳しく見ていきましょう。
不採択要因その1:企業の強みが出ていない
事業再構築補助金の公募要領には「どのように他者、既存事業と差別化し競争力強化が実現するかについて、その方法や仕組み、実施体制など、具体的に記載してください」と記載されています。
これは、補助事業によって新たな市場に挑戦する際、競合他社に勝てるかどうかを確認するための項目です。事業再構築によって新しく事業を始める場合、基本的には後発として取り組まなければならず、ここで成功するには競合他社に負けない強みが必要となります。
そのため、自社だけが持つ強みが明確に記されていなければ不採択となる可能性が高くなるのです。
企業の強みを出すポイント
- 競合他社に負けない自社の魅力をアピール
- 補助事業を掛け合わせることで競合他社に勝るストーリー作り
不採択要因その2:収益性が判断できない
国が補助金を提供するのは、その補助金を資金として高い収益を生み出す事業を行ってほしいからです。そのため、その事業によってどの程度の収益が見込めるかは、重要なポイントとなります。
もちろんほとんどの事業者は収益について記載していますが、売上・利益のみを記載するなど、内容が不足している場合が多くなっています。例えば費用の内訳や売上の算出根拠などが記載されていないと、審査員は本当に高い収益を上げられるか判断できず、不採択になりやすくなるのです。
収益性記載のポイント
- 売上・利益のみだけではなく、細かい内訳を記載
- 売上・利益の算出根拠を明確にする
不採択要因その3:市場ニーズの分析が甘い
事業再構築補助金の公募要領には、審査項目に「事業化に向けて、競合他社の動向を把握すること等を通じて市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。市場ニーズの有無を検証できているか。」と記載されています。
補助事業の計画や取り組みがどれだけ優れていたとしても、それを求めるニーズがなければ利益をあげることはできません。そのため、市場ニーズを正確に分析できているかどうかも、やはり重要なポイントとなるのです。
この分析がしっかりなされていないと判断されると収益性の高さも不透明となり、不採択になる可能性が高くなります。
市場ニーズ分析のポイント
- 市場規模や競合他社の情報を用いて分析する
- その市場にどのようなニーズがあり、顧客課題があるのかを明示する
自力作成でありがちな事業計画書の失敗点
事業計画書の内容は基本的に審査項目に沿って作成していきますが、項目や必要な書類の数も多いため、隅々まで完璧に仕上げることは難しくなっています。そこで次に、その中でも特に失敗しやすいポイントについて紹介します。
失敗点その1:書類の不備
まずそもそも書類の準備がしっかりできていない、という失敗が実は多くあります。必要な書類がアップロードされていない、もしくはアップロードした書類が別のものになってしまっているなどの単純なミスも少なくありません。
また事業計画書の内容が公募要領や事業再構築指針に沿ったものになっていない、要件を満たしていないなどの基本的な不備により不採択になることもあります。これらの初歩的なミスに関しては、チェック体制を見直すだけで防ぐことが可能。
書類に間違いや抜けが無いか、審査項目や指針に合った内容になっているかをチェックするなど、複数人で行う体制の強化を行ってください。
書類の不備を防ぐポイント
- 複数人で書類に目を通す体制の強化を行う
- 書類に間違いや抜けが無いかチェック
- 書類の審査項目や指針に合った内容になっているかチェック
失敗点その2:内容が分かりにくい
事業内容の説明が分かりにくく、不採択になってしまうことも多くあります。例えば専門用語が多く内容が理解しにくい、事業計画にストーリー性がないため因果関係が不明、などが原因として挙げられます。
事業計画書がどんなに素晴らしいものだったとしても、それを理解してもらえなければ採択されません。計画書の内容には分かりやすさや説得力も必要です。
内容をわかりやすくするポイント
- 事業計画書に因果関係がわかるストーリー性を
- 事業計画書に理解が難解となる専門用語を多用しすぎない
- とにかく理解してもらえる内容に
失敗点その3:客観的な資料の不足
分析の結果や文章そのものに説得力を出すためには、客観的な資料が必要となります。自社のみの情報だけでは、都合のいい情報を作り上げることも可能だからです。これが不足していると、審査員としては採択に踏み切ることが難しくなります。
例えば国の統計資料や業界団体の資料などを活用し、客観的に見ても妥当な計画であることを証明しましょう。
客観的な資料不足解決のポイント
- 自社だけのデータや資料などで完結させない
- 国の統計資料や業界団体の資料などを活用
- 自社以外の資料を利用し、信頼性のある情報を載せる
事業再構築補助金に採択されるための改善方法
失敗点でも改善の方法について軽く紹介していますが、そのほかにも改善のポイントはいくつか考えられます。そこで次に事業再構築補助金の改善方法を3つ紹介します。
改善方法その1:問い合わせを行う
まず事業再構築補助金が不採択となった場合、事務局のコールセンターに問い合わせすれば、なぜ不採択になったかその理由を教えてもらえます。理由に関しても内容が不十分だった部分、評価が低くなった理由など詳しく説明されます。
このフィードバックを生かせば次の採択はかなり通りやすくなるため、必ず問い合わせを行いましょう。なお採択結果の発表直後は問い合わせが殺到し、返答までに時間がかかる可能性があるため、少し時間を置くことをおすすめします。
改善方法その2:説得力のあるストーリーづくり
採択されるには事業計画書を使い、成功する事業であることをアピールする必要があります。そのため「自社の強みに設備投資や宣伝などの補助事業を掛け合わせることで、こういった効果が生まれ、競合他社に勝る魅力となる」といったストーリーづくりをしっかりと行ってください。
またこれに信用性の高い客観的資料を引用し、引用元を明確に表記することで、そのストーリーに説得力を与えることが可能です。
改善方法その3:分かりやすさや見栄えを意識する
事業計画書の内容を誰が見ても分かりやすくするためには、以下のポイントに注意しましょう。
事業計画書の内容を分かりやすくするポイント
- 専門用語を使わない
- 説明する場合には数字を使う
- 5W1Hを意識して文章をつくる
また表やグラフ、画像などを使い見栄えをよくすると、直感的にも分かりやすくできるためおすすめです。
まとめ
今回は事業再構築補助金が不採択になった場合に考えられる原因や、改善方法について詳しく紹介しました。事業再構築補助金は1度不採択になったとしても再度挑戦できるため、ぜひ今回の記事を参考に採択を目指してはいかがでしょうか。
なお株式会社High Adoption(ハイアドプション)では、事業再構築補助金やものづくり補助金の申請支援をしています。事業計画書づくりなどが難しいと感じる場合は、ぜひお気軽にご相談ください。